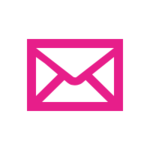近年、ゲリラ豪雨や台風による冠水で、車が浸水するリスクに不安を感じる方は多いのではないでしょうか。どこまで車が浸水したら「水没車」と判断されるのか、その明確な基準を知りたい方もいらっしゃるかと思います。
そこで、この記事では、車の浸水被害を防ぎたい方はもちろん、万が一浸水してしまった場合の対処法や水没した車に乗ることで生じるリスク、保険の適用範囲など、車を安全に守るために知っておきたい情報をご紹介いたします。
どこまで浸水したら水没車?

「水没車」という言葉はよく耳にしますが、実は法律上の明確な定義があるわけではありません。しかし、一般的には車両の内部にまで水が浸入し、走行に支障をきたしたり、電気系統やエンジンに深刻なダメージを負ったりした車を指します。
損害保険会社や中古車業界では、水に浸かった程度や被害の範囲に応じて、「水没車」「浸水車」「水害車」などの呼称が使い分けられています。
基本的には修理費用が車両の価値を大きく上回る場合や、安全な走行が困難と判断される場合に「水没車」として扱われることが多くなります。
具体的にどこまで水が浸入したら「水没車」と見なされるかは、浸水の深さによって異なり、車のリスクも変わってきます。
以下で具体的に、浸水の深さと車の影響について紹介いたします。
浸水範囲:タイヤの半分・マフラーより下
タイヤの半分、あるいはマフラーの高さよりも低い位置まで浸水した場合、比較的軽度な浸水と判断されることがあります。このレベルの浸水は、一般的に「床上浸水」には至っていない状態です。
しかし、たとえこの程度の浸水であっても、以下のようなリスクが潜んでいます。
- 下回りのサビの発生:フレームや足回り、排気系部品などが水に触れることでサビが発生しやすくなります。サビが進行すると部品の劣化を早め、将来的な故障の原因となることがあります。
- ブレーキへの影響:ブレーキディスクやパッドに水が浸入することで、一時的にブレーキの効きが悪くなったり、異音が発生したりする可能性があります。
- マフラーからの浸水:走行中にマフラーの排気口から水が逆流し、エンジン内部に水が浸入するリスクは低いですが、完全に停止している状態で長時間浸かると、ごくわずかながら水が浸入する可能性もゼロではありません。
「床上浸水」には至っていない状態であれば、すぐに走行不能になることは少ないですが、後々のトラブルを避けるためにも、必ず専門業者による点検を受けることが重要です。
浸水範囲:タイヤの半分・マフラーより上
タイヤの半分やマフラーよりも高い位置、例えばドアの下端やフロアマットの下、さらにはシートの座面まで水が浸入した場合は「床上浸水」あるいは「シート下浸水」と呼ばれる深刻な状態であり、「水没車」と見なされる可能性が非常に高くなります。
このレベルの浸水では、以下のような重大なリスクが伴います。
特に、シートの座面まで浸水した車は、JAF(日本自動車連盟)などの専門機関でも「水没車」として扱われ、走行は非常に危険とされています。
もし、浸水した車がエンジン停止している場合は、絶対に再始動を試みないでください。無理にエンジンをかけると、さらなる損傷を招く恐れがあります。速やかに専門業者に連絡し、適切な処置を受けるようにしましょう。
冠水道路の見極め方
冠水道路を走行する際は、見た目以上に危険が潜んでいることがあります。水深や路面の状況を正確に判断し、安全な走行を心がけることが重要です。
水深の目安と危険性
冠水道路を走行する際に最も重要なのは、水深を正確に見極めることです。わずかな水深でも車に深刻なダメージを与える可能性があるため、慎重な判断が求められます。
水深と車の部位の関係
一般的に、水深が深くなるほど、車へのリスクは急激に高まります。中でも、マフラー・エンジンの吸気口・フロア下の電装系部品などの位置まで水が達するかどうかが、車の故障を防ぐための重要な判断基準となります。
上記の目安は一般的なものであり、車種や車の構造によって影響の度合いは異なります。水深が浅く見えても、路面状況によっては思わぬ危険が潜んでいることを常に念頭に置いてください。
浸水により「ドアが開かない」場合の対策法は?

車が浸水した場合、水位が上がるにつれてドアに大きな水圧がかかり、自力で開けることが困難になることがあります。水深が深くなるほど水圧は増大し、人の力ではドアを開けられなくなる可能性が高くなります。
このような緊急時には、以下を参考に冷静に対処することが重要です。
水圧により「ドアの開放が困難」
もしドアが開かない場合は、車内外の水位がほぼ同じになるまで待つことで、水圧の差が解消され、ドアを開けられるようになる可能性があります。
しかし、この方法は車内が完全に浸水する状況であり、非常に危険を伴うため、次の「窓からの脱出方法」を優先的に検討し、速やかな脱出を試みてください。
窓からの脱出方法
浸水により電気系統がショートすると、パワーウィンドウが作動しなくなることがあります。このような状況では、窓からの脱出を試みることが重要な手段となります。
脱出用ハンマー(レスキューハンマー)の使用
万が一の水没や事故に備えて、脱出用ハンマー(レスキューハンマー)を車内に常備しておくと安心です。これは、窓ガラスを割って車外に脱出するための専用ツールで、シートベルトカッターが一体化されているタイプが一般的です。
使用する際は、フロントガラスではなく、サイドウィンドウの四隅を強く叩くと割れやすいとされています。フロントガラスは合わせガラスのため非常に硬く、リアガラスも車種によっては割れにくい場合があります。
窓を割ったあとは破片に注意しながら速やかに脱出し、シートベルトが外れない場合はハンマーのカッター機能で切断して脱出しましょう。
JAF(一般社団法人 日本自動車連盟)の公式サイトでは、水没時の脱出方法や脱出用ハンマーの有効性について検証結果が公開されていますので、あわせて確認しておくことをおすすめいたします。
水没した車に乗るリスク
水没した車は、見た目には問題がないように見えても、内部に深刻なダメージを抱えている可能性が非常に高く、運転を続けることは極めて危険です。
一度水没した車には、以下のような様々なリスクが潜んでおり、最悪の場合、重大な事故につながる恐れがあります。
電装系トラブルの発生

車には多くの電装部品が搭載されているため、水に浸かることでこれらの部品が故障するリスクがあります。特に、水は電気を通すため、ショートや漏電が発生しやすくなります。
エンジンの損傷・異常燃焼
エンジンが水に浸かることは、車にとって致命的なダメージを与えます。特に、エンジン内部に水が侵入すると、以下のような深刻な問題が発生します。
- ウォーターハンマー現象
エンジンの作動中に吸気口から水が吸い込まれると、燃焼室に入った水は圧縮されず、ピストンがシリンダーヘッドに激しく衝突します。その結果、コンロッドが曲がったりクランクシャフトが損傷したりすると、エンジンの主要部品が破壊される「ウォーターハンマー現象」が発生し、エンジンは再起不能となることがあります。
- 異音やエンストの発生
エンジン内部に水が残っていると、不規則な燃焼や異音が発生したり、走行中に突然エンストしたりする原因となります。
- 白煙の排出
マフラーから水蒸気を含んだ白煙が大量に出る場合は、エンジン内部に水が侵入しているサインである可能性があります。
ブレーキ・足回りの不具合
水没は、車の安全走行に直結するブレーキや足回りにも悪影響を及ぼします。これらの部品の不具合は、重大な事故につながる可能性が高いため、特に注意が必要です。
- 制動力の低下・異音
ブレーキディスクやブレーキパッドが水に濡れると、摩擦力が低下し、制動距離が伸びる可能性があります。また、泥や異物が付着することでブレーキ時に異音が発生したり、ブレーキが固着したりする原因にもなります。
- ハブベアリングの損傷
車輪を支えるハブベアリングに水が侵入すると、内部のグリスが流出し、サビが発生しやすくなります。そのため、走行中に異音が発生したり、最悪の場合は車輪が脱落したりする危険性があります。
- サスペンションやステアリング機構への影響
サスペンションの各部品やステアリング機構に水が浸入すると、サビや腐食が進み、異音や操作性の悪化を招くことがあります。その結果、走行の安定性が損なわれ、危険な状態となる可能性があります。
車内カビ・悪臭・健康被害
車内に水が浸入すると、見た目の問題だけでなく、衛生面や健康面にも深刻な影響を及ぼします。
エアバッグが作動しない可能性
衝突時に乗員の命を守るエアバッグシステムも、水没によって機能不全に陥る可能性があります。
保険の対象外となる可能性
水没による車の損害は、加入している自動車保険の車両保険で補償される場合がありますが、すべてのケースで適用されるわけではありません。
車両保険には、一般的に「一般型」と「エコノミー型」の2種類があり、補償範囲が異なります。
ご自身の車両保険の契約内容が、水害をカバーしているかを必ず保険会社に確認するようにしてください。
また、故意に冠水路に進入して水没させた場合など、運転者の過失が著しいと判断される場合は、保険が適用されない可能性もあります。
再販価値の大幅減少/査定ゼロ
「床上浸水」あるいは「シート下浸水」により「水没車」と見なされた車は、その後の「再販価値が大幅に低下」するか「査定額がゼロ」になることがほとんどです。
中古車市場では、水没車は「冠水歴車」として扱われ、修復歴車以上に敬遠される傾向にあります。その理由は、上記で述べたような見えない部分の不具合や、将来的な故障リスクが非常に高いと判断されるためです。
そのため、車両を売却する際には、水没した事実を告知する義務があり、これを怠ると後々トラブルになる可能性があります。
多くの買取業者では、水没車は買取不可となるか、解体費用を差し引いたごくわずかな金額での引き取りとなるのが実情です。
弊社でも水没車の買取りを行っておりますが、他の買取業者の動向に左右されることなく査定額を判断いたしますので、お気軽にご相談ください!
水没車を廃車にするなら「困った車買取り専門®船橋店」へ!
前述したように、一度水没した車は、一見すると問題なく見えても、内部では深刻なダメージを受けている可能性が高く、再販価値が大幅に減少することが珍しくありません。
そんなときは、千葉県・船橋にある「困った車買取り専門®船橋店」へお任せください!「困った車買取専門®船橋店」では、冠水車や水没車の買取も行っております。
例え水没車であっても、それはお客様にとって大切な愛車です。「頼んでよかった」「相談してよかった」と思っていただけるよう、誠実にご対応いたします。
以下では、「困った車買取り専門®船橋店」のポイントを5つ紹介いたします!

①わかりやすい料金提示!
きっちり・ハッキリ・しっかりを心がけた、透明性の高い料金提示をいたします。
②当日から数日以内に引き取り可能!
ご依頼をいただいてから、最短即日で引き取りに伺います。お急ぎの廃車手続きもスピーディーに対応可能です。
③引き取り場所の遠近は問いません!
船橋近郊はもちろん、千葉県全域や隣接する市区町村(茨城県・東京都・埼玉県など)の遠方エリアでも柔軟に対応いたします!「廃車にしたいけど持ち込めない…」という方も安心してご相談ください。
④廃車に必要な書類や手続きは一括代行いたします!
運輸局などへの届出やナンバー返却など、面倒な作業はすべてお任せください。廃車をご検討されている方は、お気軽に無料査定をお試しください。
⑤日曜日や祝日も営業!
日曜・祝日も営業しているので、週末や祝日しか時間が取れない方も大丈夫です。
よくある質問
Q.どこまで浸水したら「水没車」と判断されるの?
明確な法律上の定義はありませんが、一般的には「シートの座面まで水が浸かる」または「電装系やエンジンに深刻なダメージを受けた」状態の車が水没車とされます。走行に支障があり、修理費用が車両の価値を大幅に超える場合は、水没車と見なされます。
Q.車が浸水したらエンジンをかけてはいけないのはなぜ?
水がエンジンの吸気口に入っていると、再始動時に「ウォーターハンマー現象※」が起こり、ピストンやコンロッドなどが破損してしまいます。結果として、エンジンが再起不能になるため、専門業者に見てもらうまでは絶対にエンジンをかけないようにしましょう。
※ウォーターハンマー現象:ウォーターハンマー現象とは、水を吸い込んだことでエンジン内部が壊れ、最悪の場合エンジンが再起不能になる現象です。
Q.車が浸水したら何をすべき?最初に取る行動は?
エンジンをかけず、すぐに車外へ避難してください。その後、JAFや保険会社など専門業者に連絡し、レッカーや点検の手配を依頼しましょう。車両が水に浸かった時間が長いほど、電装系やエンジンのダメージは大きくなります。
Q.冠水道路の水位はどのくらいまでなら走行できる?
一般的には水深20cm以下であれば走行可能とされています。目安としては「縁石(約15㎝)が見えているかどうか」。ただし、ブレーキ性能の低下や見えない側溝への脱輪リスクもあるため、避けるのが望ましいです。
Q.水没車に乗るデメリットは?
エンジンや電装系が故障しやすく、ブレーキ性能も低下するだけでなく、カビや悪臭、エアバッグの不作動リスクがあります。また、手放す際に査定額が大幅に下がる可能性があり、安全・衛生・経済面で大きなリスクがあります。
Q.水没車は保険対応で補償される?
加入している車両保険のタイプによって異なります。「一般型(フルカバー)」であれば、水害も補償対象になることが多いですが、「エコノミー型」では、補償されないケースもあります。契約内容を確認の上、必要に応じて見直しをおすすめします。
まとめ
この記事では、水没車の定義からその危険性などを解説してきました。
一般的に、タイヤの半分やマフラーより上まで浸水した車は「水没車」と判断され、走行不能になるだけでなく、深刻なトラブルを引き起こすリスクがあります。
冠水道路に遭遇した際は、見た目以上に深さがあることも多いため、無理に進入することは絶対に避けるようにしてください。
「困った車買取り専門®船橋店」の査定は、他社の動向に左右されることなく、お客様のご期待に応える内容であると自負しております。
どんな状態のお車でも構いませんので、廃車をご検討される際は、お気軽にご相談ください!